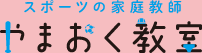最近のフィットネス業界では、クラブの定番であったプールをあえて排除し、フィットネスジムとしては比較的狭い80〜120坪の敷地に、マシンジム特化型スタイルでウエイトトレーニングやランニング用のマシンだけを設置した24時間ジムが増えています。プールがないだけで設備費と維持費はかなり低く抑えられる上、水回りのトラブルなどに対応するスタッフを常駐させる必要もなく、初期投資とランニングコストのいずれも大幅に削減できる、一見すると人件費も競合他社に比べて圧倒的に低く抑えられているのが理由です。
施設が増えると心配されることも増えるのですが、健康寿命を伸ばそうと中高年者は真面目に通われ、無理をし過ぎたことで怪我をしたり故障を訴える例も増えています。
例えば、運動による肩の痛みを大別すると、過去には野球、テニス、水泳、ゴルフなどの肩(腕)を大きく動かすことによるものや、サッカー、バスケットボールなどの打撲などの衝撃によるものでしたが、中高年になるにつれ肩を構成するいずれの部分も強度が少しずつ低下した上に、肩をあまり動かさない生活をしていると柔軟性だけじゃなく弾力性も無くなり、血行も悪くなったり傷つきやすくなります。ちょっとしたことで肩関節周辺のどこかに損傷が生じ、炎症によって痛みを感じるようになります。
また中高年の場合は回復にも時間がかかったり、慢性化しやすいといった傾向があるので注意が必要です。肩の痛みは、腱板断裂や骨折など重症化していることもありますので自己判断せず、怪我の予防のため、身体の仕組み・働きを理解し健康生活に役立てるように努めましょう。

肩関節は、主に腕の骨(上腕骨)、肩甲骨、鎖骨から構成されています。上腕骨の先端にある骨頭と呼ばれる球状の部分が、肩甲骨関節窩(くぼみ)にはまり込む構造になっている肩甲上腕関節のことを一般に肩関節と呼んでいます。周辺には肩甲骨と鎖骨で構成される肩鎖関節や、胸骨と鎖骨で構成される胸鎖関節などが複数の関節が存在していますから、人間の関節の中で最も大きく動くのが関節です。腕を伸ばして回してみると、ほとんど全方向に動くようにできています。肩関節は他の関節と比べて接触面が浅く不安定ですが、こうした動きを支えるために腱板、滑液包、靭帯、筋肉が複雑に組み合わさっています。
肩の痛みだけで四十肩・五十肩と決めつけるわけにもいきません。肩の痛みの原因となる病気や障害は、ほかにもたくさんあるからです。例えば、腱板に石灰分がたまるもの、スポーツの負担によるもの、あるいは頸椎の変性や、狭心症・心筋梗塞の前兆という例もあります。こうした病気などは、いずれも放置していると治りにくくなったり、重大な発作につながりかねません。肩の痛みを軽く考えず、冷湿布などで痛みが引かない場合には早めに医療機関に受診するようにし、その原因と予防解消法についても学んでおきましょう。
上腕の後ろ側の大きな上腕三頭筋があります。上腕筋群の中で最も体積が大きい筋肉で長頭、外側頭、内側頭の三頭で構成されています。肩甲骨・上腕骨・尺骨についており、 肘関節を伸展させ、手関節を内転および伸展させています。例えば腕立て伏せや何か物を押すといった動作で肘筋と共に肘関節の伸展動作に大きく貢献します。
三頭のうち長頭だけが肩甲骨に付着するため、肘関節の伸展動作に加え、肩関節の伸展動作にも関与しています。内側頭は肘関節伸展に伴う後方関節包の挟み込みを防止するという役割も担っています。上腕三頭筋のうちどの部分にストレスを与えるかによって肩関節の角度を考慮しなければならない時もあります。
24時間ジム等に設置されていて人気のある胸を鍛えるプレス系のマシンでは、ついつい重たい負荷でやりたくなる種目であるために、動作の終始に渡って上腕三頭筋にストレスを与え続けるだけでなく、肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、大円筋、小円筋で受け続けてしまうために、鈍い痛みを伴わせてしまうケースがあります。そうなると腕を動かすこともできなくなったり、肩が上がらず物を投げることができないといった腱板損傷のような症状が現れたりします。
肩痛予防改善のためのやまおく体操
・肘かわし体操
肘かわし体操は、肩周囲の筋肉を刺激することができ、上半身でも大きな部分を占める三角筋周辺の筋肉群をしっかりして姿勢の良い身体造りが出来ます。
また、ボクサーやラグビー選手の上半身を見てわかるように、肩周囲が盛り上がっていると思います。このような強くたくましい身体のアスリートは、逆に慢性的な肩こりに悩まされている方も少なくないので、なるためには肘かわし体操のような三角筋周辺の筋肉群を刺激するトレーニングは、欠かせません。
腕の最上部に位置する上腕三角筋も同時に刺激出来るため、二の腕の振袖状態が、気になる方にも、お勧めです。
・肘引き体操
肩を覆う筋肉(三角筋)は、上半身の中で、比較的体積の大きい部位です。三角筋は、前部・中部・後部に分けられ、全て肩関節を動かすのに異なる機能を持っています。 肘引き体操では、前部・中部・後部の全ての部分を鍛えられます。
肩関節周辺の可動域を広げ、日常生活だけでなく、あらゆるスポーツにもお役に立てます。目線より上に、腕をあげることが、少ない一般の方には、三角筋を鍛えることで、なで肩等も解消されますので、衣装を着られても、姿勢良く、健康的に見えます。
・立って膝内捻り体操
立って膝内捻り体操は、腰痛や肩こりなどお悩みの方にも、お勧めですが、運動不足や日々の生活で身体の硬さや重さを感じている方にも必見です。
バリスティックな動きによって内転筋、腸腰筋、深層外旋六筋を刺激するトレーニングです。
これらのやまおく体操を使った肩痛予防改善のためのやまおく体操プログラムは…
肘かわし体操+肘引き体操を交互3~5周行なって、立って膝内捻り体操を1周行うプログラムを3~5周行うと更に効果的です。
また、出来そうでしたら、肘かわし(片手ダンベル)を試してみてください。肘かわし(片手ダンベル)は、ダンベルを上げるときに前部と中部、下げるときに後部に対してバネのような動作を誘導するトレーニングです。
三角筋に程良い負荷を与えながら、肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、大円筋、小円筋の動きも滑らかにします。 日常生活ではあまり使われないので肩の筋肉は痩せてしまいがちですが、肘かわし(片手ダンベル)には、代謝を上げ、痩せやすい体質に変わる、そして肩こりの解消という効果があります。
気圧が下がって湿度が上がると、よくある首の寝違えみたいな症状も、知らない間に良くなりますよ。