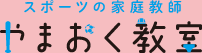早歩きのススメ Ⅹ
| 運動
食欲をコントロールするネットワークの1つに消化管ホルモンがあります。
消化管ホルモンには、胃から分泌される食欲促進ホルモンのグレリン、
腸管から分泌される食欲抑制ホルモンのPYY・GLP-1があります。
満腹感や空腹感は、これらのホルモンの影響を少なからず受けています。
PYY・GLP-1は、運動することによって分泌が促されます。
最大酸素摂取量が得られる強度の運動を100%とすると、
50%強度で60分運動したところ、PYY・GLP-1の分泌量が増し、
食欲が抑制されることが分かっています。
60分の早歩きによって、食欲を抑制することが出来ます。

定機器の無い運動指導の現場では、主観的運動強度RPEを用いると良いです。
杉谷泰造さんと、大西徹平くんを比べたことがあります。
馬の競技では、同じ競技であるのに、
杉谷泰造さんの方が、指標が低かったのに対して、
同じトレーニングでは、大西徹平くんの方が、指標が低かったのです。
馬術競技での出力を下げるために、大西くんには、ある時期厳しいトレーニングを課して
スケールを少し大きくしたところ、馬術競技での指標が下がりました。
馬術の上手い下手を口で説明するのが難しいので、この指標を揃えることで、
経験は、抜けないにしろ、技術面は、ある程度揃うのでは無いかという仮説からです。
また、トレーニングでは、杉谷泰造さんは、追い込むのが好きな性格ですので、
シーズン中は、普段の約6割で行なって頂くようにしたところ、
コンディションが崩れなくなったのと、我慢度が高いために傷つけていた糖代謝の部分も
安定させることが出来ました。恐らく遺伝で糖尿の気があったかと思います。
同じ運動であっても、ヒトによって感じる運動のキツさが、異なりますので、
この指標を見なくても、顔色で伺えるようになると良いですね。