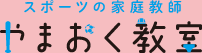運動能力の個人差は、何処で見る?!
| 運動
あのヒトは、あちらのヒトより運動能力がある…とよく表現されることがあります。そのヒトの運動能力は、一体、何処を見れば良いのでしょう?
生理学では、心肺機能が何処までの運動の強さに耐えられるか?を、そのヒトの運動能力として評価しています。もちろん、運動能力は、ヒトによって異なります。
無理せずに運動を行うためには、まず自分の運動能力の限界を知ることが大切です。

一般の成人男性では、1分間に体重辺り30~40mlの酸素を消費出来ます。
スポーツ選手は、1分間に体重辺り50~60mlの酸素を消費出来ます。学生時代に、マラソンの元選手だった瀬古さんは、70mlと言われていました。
熟年の男性では、1分間に体重辺り20mlの酸素を消費出来ます。
この限界を知らずに無理をしてしまうと、ジョギング中に倒れたりなどの運動中の突然死につながることもあります。せっかく健康のための有酸素性運動ですので、注意が必要ですね。