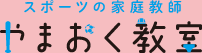1日の気温差が大きいと体温が体外に奪われそうになるのを防ぐ防衛反応によって身体が縮こまります。筋肉が伸び縮みし難くなる、身体が硬くなったり、疲れやすくなったりします。
首コリとは、首の後ろの筋肉が緊張し血行が悪くなってこわばる状態です。長時間同じ姿勢を続けたり、スマートフォンやパソコンを長時間使用したりすることが主な原因で、痛みやだるさ、頭痛、めまいなどの症状を引き起こすことがあります。
主な症状
* 首の痛み、だるさ、重さ
* 頭痛やめまい
* 肩こり、腕のだるさ
* 吐き気や食欲不振などの胃腸障害
* 慢性的な倦怠感
首には血管・気管・神経など、大切な器官が集中していますが、首後部には頭板状筋・頸板状筋・頭棘筋と筋肉が少なく、重い頭を支えるために首の骨は前方に向かって湾曲(横から見るとS字カーブ)しています。この形が、スイカ約1個分もある頭の重みをうまく分散しているのです。上肢(肩甲帯・腕・手)は首周辺の筋肉からぶら下がっていますので、直接首や肩周囲の筋肉の負担にもなっています。

頭板状筋は、頸椎および胸椎の棘突起を起始とし、外側上方に向かって走り、側頭骨乳様突起、後頭骨に付着しています。
頸板状筋は、胸椎の棘突起を起始とし、外側上方に向かって走り、頸椎に付着する。 片側が収縮するとその方向に首が回転します。
頭棘筋は、第1~第7頸椎横突起を起始とし、前側上方に向かって走り、大後頭孔に付着しています。頭半棘筋の一部ともされ、頭部および脊柱の後屈、側屈を行います。
血液は、心臓が送り込む液体で、体内の循環系統を通り酸素やその他の物質を体内の全ての細胞に運びます。平均的な成人ですと、大体5リットルの血液が体内を流れています。透明な液体である血漿と、赤と白の血球、血小板がその中で漂っています。白血球は感染症と戦い、血小板は血液を凝固させる働きをし、赤血球は酸素を全身に供給しています。赤血球は3分の1がヘモグロビンという鉄分豊富なたんぱく質で、酸素と結合して血液は赤さび色になります。
ヘモグロビンはヘモクロームの種類で血液の色に大きな影響を与えるたんぱく質です。他の生物は、それぞれ異なるたんぱく質がありますので、全ての動物がヘモグロビンを使っているわけではありません。例えば、タコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどの軟体動物や節足動物の血液は高濃度のヘモシアニンが含まれているため青色です。血液の色は、体内で血液がどのように酸素を動かすかによって決まるというものでもありますから、全ての動物の血液が赤いわけではありません。
人間は、息を引き取って直ぐは細胞が生きていますが、心臓や呼吸が止まり細胞に酸素が運搬されなくなると低酸素状態に陥り、細胞が損傷して死んでいきます。細菌やウィルス感染、自己免疫や遺伝的異常、放射線等によっても細胞が損傷していきますが、老化や運動不足は、細胞に酸素を運搬する量を減らした状態と同じことですから、活動的だった頃より細胞に酸素が運搬されなくなると、徐々に細胞を損傷させて筋肉が痩せていきます。一時的に入浴やマッサージなどで血流を促すことで首こりを解消させることも出来ますが、他の部分に比べて筋肉量が少ないですから、硬くなりやすく疲れやすくなっていきます。
首コリ予防改善のためのやまおく体操
・座って斜め上体振り子体操
腹筋には、腹直筋と腹斜筋から、構成されています。腹斜筋は、腹直筋に比べ、刺激の与えにくい部位ですが、座って斜め上体振り子体操は、腹斜筋を刺激出来るトレーニングです。

脊柱起立筋や腰方形筋等も刺激できますので、正しい姿勢作りや、腰痛、背部痛予防につながります。背中のアーチをかっちり固定して、動作することが、大切です。体幹は、どの筋力トレーニングにも重要な項目ですので、鍛えておきましょう。
・足首コロコロ体操
足首コロコロ体操は、使い方を忘れている臀筋群やハムストリングを刺激するトレーニングです。股関節が、よりダイナミックに動くと血流が促され、むくみや冷えなどの症状も改善します。臀筋群やハムストリングが、骨盤を引っ張るので、腰痛のもとである丸腰や、その反動で、首や肩が、前に出る悪姿勢も改善します。ヒップラインも綺麗になります。
歩くという動作は、一見、股関節を前後に動かすように見えていますが、本来は、股関節を内側や外側に微妙に回旋させて移動しています。こうした関節の遊びが、あるため、正しい歩行や、美しい歩き方が、出来ます。臀筋群や、ハムストリングが、緩んでいると、股関節は、屈伸するだけの単調な動きになります。そうなると、太い脚と悪い姿勢が身についていきます。股関節捻り動作が、大切になります。
・あぐらストレッチ体操
あぐらストレッチ体操は、具体的には、股関節のインナーマッスルの腸腰筋、臀部の大臀筋、中臀筋、小臀筋、大腿のハムストリングと呼ばれるハムストリングと呼ばれる大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋、、太腿四頭筋、内転筋の弾力性が、増して、股関節をスムーズに動かせるようになります。
股関節が硬いままでは、可動域も制限され、身体の動きが鈍くなりがちです。そのため代謝の低下により、身体が、冷えて、お尻やお腹まわりに脂肪がつきやすくなります。あぐらストレッチ体操で、筋肉を刺激し、関節の動きを良くすると、血行が良くなります。下半身太りやむくみ、冷え、ぽっこりお腹、猫背などを改善できます。
これらのやまおく体操を使った首コリ予防改善のためのやまおく体操プログラムは…
(座って斜め上体振り子体操+あぐらストレッチ体操)を交互に3周+足首コロコロ体操を1周を3〜5周行います。第1〜5腰椎は、第1〜5頸椎の動きと連動していますから、筋肉の少ない首に対してアプローチするより、大きな筋肉のある腰に対してアプローチする方が安全に運動効果を導き出せます。
たくさんある筋トレ方法のなかで、腰引き (両手回し)は、首コリ予防解消だけでなく、多くの筋肉を動かす運動ですので、カロリーの消費量が多くダイエットにも効果的という特徴がありますので、是非試してみてください。